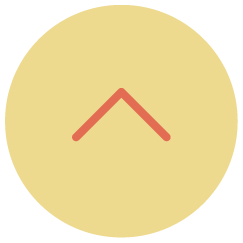次代の社会を担うための行動計画
1.
すべての職員を対象に雇用環境の整備とマネジメントをとおすともに、次世代育成支援について、貢献できる組織となるため、次のように行動計画を策定する
2.計画期間
2025年4月1日~2027年3月31日までの2年間とする。
3.次代の社会を担うための行動計画
目標1「子どもの出生時における育児休業の取得100%を目指す。」
【現状評価】
24度の正規職員の育児休暇取得率については女性100%、男性50%の取得率状況となります。制度の認識、過去の取得事例を通して浸透してきたと思われます。また、事前に部署内での相談、総務窓口における関わり、取得経験職員からの助言もあり安心して取得できる環境に整ってきたと思われます。しかし、原則復職時は育児休暇前の部署での復職となります。配送現場では帰着時間の問題から施設への迎えに影響が出ています。安心して子育てと仕事の両立した環境に至っていない実態があります。限られた部署、配送現場での役割から個別事情については協議をすすめる必要があります。また、帰着時間の課題については全体で是正していく必要もあります。
【対策】
・2025年8月~
所属長に対する学習会の場を設け、育児休暇に対する理解を深めます。
・2025年10月~
部内報などによる職員周知します。
・2026年1月~
対象者に向けて育児休暇制度(特別休暇)の助言と取得並びに情報提供を総務より行います。
目標2「年休取得促進策を実施し、一人当たりの年次有給休暇取得日数を増加させる」
【現状評価と認識】
厚生労働省の就労条件総合調査によると労働者の年次有給休暇の取得率は65.3%(前年差+3.2%)となっています。また、1企業平均年間休日総数112.1日(前年差+1.4日)となっています。これらは2019年に施行された「年5日取得義務化」による年々上昇、企業の意識改革(休暇取得の推奨・放火制度の見直し)、労働者の意識変化(ワークライフバランス・心身の健康意識の高まり)が影響していると思われます。生協しまねの有休取得率はゼネラル職員75.6%(前年差▲2.1%)、エリア職員84.3%(前年差▲2.3%)、定時職員88.1%(+0.4%)となっています。前年差で下回るものの高い水準となっています。しかし、人手不足が影響し支所を中心とした責任者が取得しづらい環境にあります。人手不足の解消、組織全体での異動タイミングの配慮、取得計画の平準化が求められます。
【対策】
・2025年8月~
個別の取得差を少なくするため、月次で個人別の取得状況を所属長へ発信し取得が少ない職員に対して取得計画を検討します。
・2026年1月~
管理者の取得率のバラつきがある実態に対して、個別指導の有無判断と取得しやすい環境づくりサポートを行います。
目標3「所定外労働時間の削減・・・月20時間以内を目指します」
【現状認識】
これまでにも1人あたり平均所定外労働時間20時間を目標に取り組んでいますが、24年度23.9時間(計画差+3.9時間)で未達成の状況になります。前年との関係では▲0.3時間と減少しました。年間通じての人手不足により、責任者中心に負荷が高まっている状況です。責任者と担当者との差が大きく、役割と責任の明確な認識の基での運営が急務となっています。
【対策】
・2025年9月~
責任者のしごとの組み立てや役割を明確にし、仕事の質の向上を図るための学習機会を設けます
・2026年2月~
管理職へデータ提供を継続し、学習機会を通じて業務効率と人件費への意識を高めます。
・2026年3月~
事業所毎に早帰りDayを設定など、ワークライフバランスの浸透を目指します。
・2026年7月~
配送実態の把握。配送ポイント数と帰着時間から配送環境の平準化を図ります。
4.行動計画を実施していくための組織体制
- 次世代育成支援対策行動計画を役職員内に徹底し、組織として目標達成を目指していきます。管理部総務チームを窓口部署とし、事務局機能として各部署との連携を担います。
- 事務局の役割
・全役職員への行動計画の趣旨について周知徹底及び教育の推進を図る。
・目標達成実現のための進捗管理、部署間連携のための調整機能を担う。
・状況報告、課題、問題点の発信と整理、対策に向けた活動提起。
・実情に応じた対応策の修正、補強を柔軟に実施する。
5.行動計画の周知
- 各部署所属長を通して部内職員への周知及びワークフローを活用して計画内容を閲覧できるようにする。
- 生協しまねのホームページ上にも行動計画を掲載し、内外への公表及び閲覧ができるようにする。